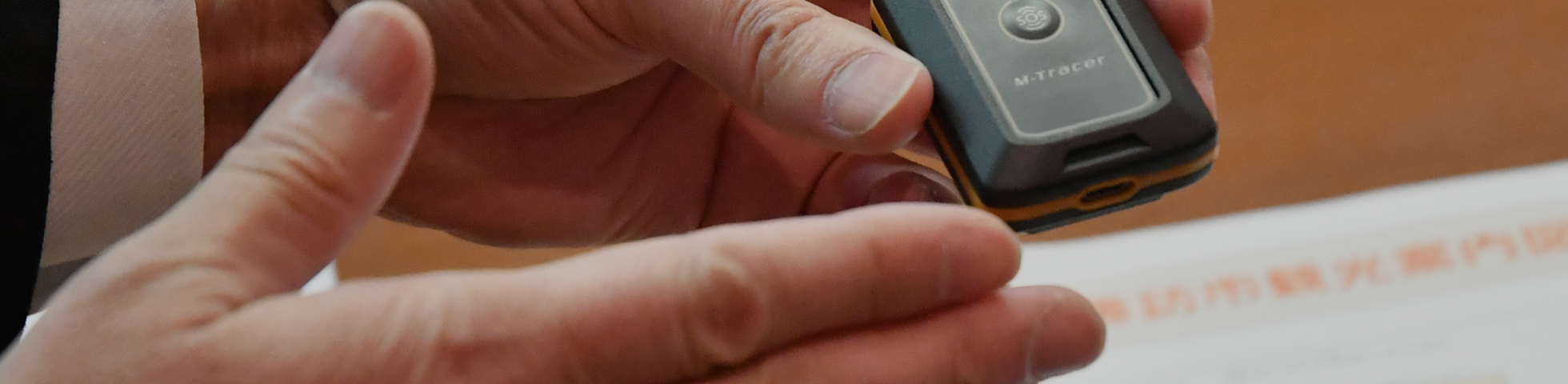本記事は2022年11月に取材した内容を基にしています。掲載当時の情報をお伝えしておりますが、一部の情報が古くなっている可能性があります。最新の状況や詳細については、関連情報をご確認ください。
長野県は長距離走が盛んで、特に駅伝に対する熱は並々ならぬものがある。その中でも県内の一大イベントとして定着しているのが、今年で第72回目を迎える「長野県縦断駅伝競走大会」だ。県内の郡市対抗大会で、晩秋の信濃路を北から南に走り継ぐ風物詩。この大会に2022年から、M-Tracerが導入。どのような経緯と効果があったのか。信州に連なる駅伝の系譜とともに、デバイスがもたらす未来を展望していく。
【第4回】各種大会が 世代間の「伝える」場所に
各種大会が 世代間の「伝える」場所に
2023年1月22日、広島市。平和記念公園前発着の7区間48.0kmで争う天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会が行われた。コロナ禍での中止を挟んで3年ぶりの開催。主催者発表で約30万人が沿道で声援を送ったこの大会で、長野は大会新をマークして2連覇を果たした。
7区間のうち1区(7km)、4区(5km)、5区(8.5km)は佐久長聖高校の選手がエントリー。4区の山口竣平が区間新となる14分2秒をマークして首位に立ち、大会MVPにも選ばれた。レースはその後も長野が首位をキープ。最長13kmの最終7区は上野裕一郎。半月前には監督を務める立教大学を55年ぶりの箱根駅伝出場に導き、脚光を浴びていた。出身は佐久市で、佐久長聖高校で育った。
大学生のトップランナーたちは、年始の箱根駅伝を終えてすぐに長野の強化合宿に合流する。実業団選手であれば、元旦のニューイヤー駅伝が終わったばかりのケースも。生まれ故郷から羽ばたいた後にも、選手たちの多くは郷土をかえりみる。自身が育ってきた来し方に思いを馳せつつ、年下の選手に対しても自然とマインドを継承していく。高校生と中学生も同様。世代間で、駅伝長野の見えない「たすき」が繋がれる。

長野陸上競技協会の北島正孝・駅伝部長は言う。
「コーチの方から色々と言わなくても、年下の選手は先輩を見て学んでいます。挨拶の仕方もそうだし、トイレのスリッパをきれいにそろえたり。集団生活をする上でお互いが気持ちよく過ごせるための気配りを自然と学んでくれていて、それも一つの成長過程ではないかと思っています」
そして、ミーティングでは「全国」「世界」といったハイレベルの水準を意識付ける。こうして、目線を引き上げてより大きな舞台へと羽ばたいていくよう促す。長野県縦断駅伝を主催する信濃毎日新聞社の有賀覚・事業局長は言う。「陸協さんの中で一生懸命、全国というよりも世界に旅立てる選手を輩出したいと言うことで、都道府県対抗駅伝なども含めて情熱を持って取り組んでくださっています。そうした部分と縦断駅伝もリンクして、噛み合っているのかもしれません」と話す。

(長野市陸上競技協会提供)
M-Tracerの活用 さらなる広がりに期待
そうした“駅伝力”の表れであり、源でもある長野県縦断駅伝。大きな変革を経て生まれ変わり、新たにM-Tracerで価値を最大化していく。2022年の試験的な導入はCATV中継への活用にとどまったが、今後はどのような活用方法が考えられるだろうか。
リアルタイムの位置情報を、それぞれの立場が把握することによって大きなメリットが生まれる。まずチームとしてはどうか。上伊那の丸山信一氏は「今はチームの人間がコースの沿道に立って指示を出すこともルール上できません。全体を把握することによって、指示は出せないまでも、自分のチームがどこにいてライバルがどこにいるのかがわかるだけでも大きいと思います」と見通す。

現状のインターフェースではチーム間の距離などは表示されないが、技術的には可能。それが可視化できれば、なお有用になるかもしれない。もちろんチームだけでなく、運営や観客、中継にも大いに役立つだろう。中継の導入自体は各チームとも好意的な受け止めだったといい、丸山氏は「各チームの監督も、中継してくれること自体はすごくいいことだと話をしていました。全チームを映してくれますし、良かったと思います」と話す。
運営サイドも同様だ。渋滞を避けるなどの理由から、スタッフはコースに入れない。しかし、「このデバイスがあれば場所を把握できますし、正確なタイミングであらかじめ次の準備や指示に移ることもできると思います」と北島駅伝部長。さらに、「繰り上げスタートが発生する場合も前もって予期できるので、慌てなくて済むのではないでしょうか」と利点を話す。

そうしたデータを何大会も積み重ねることによって、さらに円滑な大会運営につなげることも可能。「データが蓄積されてきて傾向などが読めたら、例えば繰り上げをあと5分遅らせることによって、沿道の方も(見た目の)順位変動に惑わされずずっと見られるようになるかもしれません」という。「全体を常に把握できるという意味では安心ですし、蓄積によって新たなものも見えてくるかもしれない。メリットは非常に大きいと思います」
たすきと思いをつなぎ 目線は最高峰の「世界」へ
改良と改善を加えながら、未来へつなぐ。
「幸いにして我々の先輩たちが築いてきてくれたものはまだ何とか残せているので、できるだけ続けていきたいと思っています。全県下に広がっているコンテンツですし、今後も大事にしていかなければいけないと思います」と有賀事業局長。局内にはRUNプロモーション室というセクションを設置してあり、長野県縦断駅伝のほか長野マラソン、松本マラソン、安曇野ハーフマラソン、軽井沢ハーフマラソンを5大事業としてノウハウを共有しながら運営している。

「駅伝や陸上に限らず少子高齢化で競技人口は減っていますし、一方で競技役員の方々は高齢化がどんどん進んでいます。これを何とか次の世代に繋いでいかなければいけない。この課題はどんな競技でも一緒だと思うんです」
その一助となる要素が、M-Tracerでもある。
有賀局長は続ける。
「だから、その中で少しでも新しいことを取り入れながら続けていくことが大切です。8時間の生放送なんて通常ならできないレベルのものなので、これを本当に一つの価値として今後に生かしていけたらと思いますし、それによってスポンサーをかなり確保できるのではないかと期待しています」

冬の寒さに耐えながら、夏の暑さに灼かれながら。信州の地では連綿とランナーたちが汗を流し、思いを繋いできた。指導者たちは熱意を持って成長を見守り、時には助言をしながら、大勢の目を経てランナーを育てていく土壌が伝統的にある。
長野陸上競技協会の普及強化委員長でもある長野東高校の横打史雄監督は「(全国高校駅伝で優勝できたのは)本当にいろんな人の支えがあってこそ。オール長野の態勢で、それこそ地域の指導者の方々の熱意があったからだと思っています」と強調する。

長野東高校はまた、地元とも密接に関わりながら取り組みを続けている。長野市内で共同生活を送っている選手たちは、地域の運動会に補助員として参加したり、どんど焼きにも出たり。地元の支援者たちは逆に、コースを整備したり応援の横断幕を作ったり、差し入れをしたり。愛し、愛される幸せな関係性が構築されている。
これは一つの例。長野県における多くの地域に、駅伝は今なお深く根付いている。その象徴の一つが長野県縦断駅伝。それも一つのファクターとしながら“駅伝王国”と称されるまでに高い競技力を練り上げてきた。佐久長聖高校から順天堂大学に進んだ吉岡大翔も、長野東高校と同じ地域の川中島ランニングクラブ出身。U20世界選手権にも出場しており、男子5000mの日本高校記録保持者として飛躍に期待がかかる。
たすきをつなぎ、想いをつなぐ。風を切って疾走する。その営みは、これまでもこれからも。走り続けるロードの先には、見果てぬ「世界」への夢が広がっている。